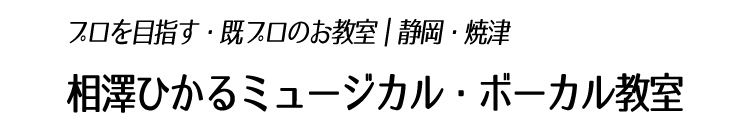オーディション対策合同特別レッスンレポ【2025年8月】ミュージカル
この少人数オーディション対策レッスンから中央で活躍する方続出❗️
2024.10.27ミュージカル「アニー」モリー役合格❗️気づかないうちに染み込んだ技術が合格へと導きます❗️
プロを目指さなくても、スキルアップや技術維持、引き出しを増やす方も❗️
今年のミュージカルレッスン2回目は、有名なミュージカルのシーンスタディに挑戦いただきました。今回も2時間みっちり集中しましたよ!前回とは全く違った作品になりましたね。
特別レッスンの週に名古屋での公演を控えた生徒さんも、最後の最後まで表現力を磨きました!
来月からはいよいよ実践の作品レッスンに入ります。さらに高め合っていきましょう!
今回も気づき・感想をシェアさせていただいておりますが、とてもいいところに気づけておりました(拍手)
このページの最後に、劇団四季創設者の「役者とは」を掲載しました。ぜひ最後までご覧ください。
お芝居のお稽古に参加する際の心得
①現場での心構え
舞台やレッスンの現場では、監督や演出家の指示が最優先です。自宅で準備してきたアイデアがあっても、それが採用されないことはよくあります(案がひとつしかない、考察が浅いなどの理由で)。その際に、自分の考えに固執したり、反発する態度をとったり、落ち込んでしまうのはプロの役者としてふさわしくありません。指示を受けたら「はい!」と気持ちよく返事をし、即座に対応していきましょう。
②見学や待機時間の過ごし方
本番やレッスンでは、出番以外の待機時間や見学時間が長くなることもあります。しかし、舞台づくりはチームで行うもの。他の人の演技やアドバイスを観察することも、学びの一部です。練習生であれば、なおさら「自分に言われたこと」として受け止める姿勢が大切です。注意点や修正点をすぐに自分の演技に取り入れられるよう、集中して見学し、メモを取りながら学びましょう。
③ミスをした時は
演技中に間違えて止めてしまった場合は、「申し訳ありません、もう一度やらせてください」と、すぐに申し出ましょう。その場合は、次のスタートの指示を待つこと。勝手にやり直して演じ始めてはいけません。
このレッスンを受けると?
このレッスンでは「セリフの読みっこをしてアドバイスをもらう」や「台本を持ったままなんとなく演劇っぽいことをする」「みんなで楽しく歌う」ような、生ぬるいレッスンは行いません。プロとして活躍するために絶対に避けては通れない基礎技術を、徹底的に鍛え上げたい方向けの訓練の場にしたいと考えています。
舞台経験がある方もそうでない方も、プロの現場で求められるレベルに到達するために、一般的なスクールとは全く異なる視点と方法でトレーニングを行います。オーディションは受けないけれど、表現力を磨いて自身の活動、演奏やダンスに活かしたいという方もご参加いただいております。
①今までの経験が覆(くつがえ)る!圧倒的な気づきが得られる!
「こんな練習初めて!」「別のスクールでやったことあったけど、こんな意味があったなんて!」「言われた通りに動いていただけだった…」「市民ミュージカルと全然違う」「これ、他の活動にも応用できそう!」「こっちのレッスンのほうがいい」
経験の有無に関わらず、レッスンを受けるたびに、きっとたくさんの「!」に出会えるはずです。「お芝居では役になりきればいい」「かっこいい自分をみてもらいたい」のように、表面的で曖昧な演技のままでは、お遊戯会的演技から脱出できません。お芝居は動機と根拠で成り立っています。このレッスンを通して、”お仕事”として通用する本物のお芝居を学んでいただきます。
受講者の感想を以下に毎回シェアさせていただいております。次回へのヒントも多いため、受講者は必ずご一読ください。
②このレッスンでは失敗は恐れず思い切って!
ここでは、頭をフル回転させ、考察してきたことを積極的に試していただく場です。完璧にできなくてもうまくいかなくても大丈夫。現場同様課題や考察を持ち込むことが大切なのです。”ただ参加する”ような受け身では上達もしませんし合格できません。オーディションや本番で最高のパフォーマンスを発揮するために、ここでたくさん失敗し、本物の感覚を正しく体験体感していただきたいと思っています。
③継続参加で結果が出る!
このレッスンは、継続して参加すること(特に5回目以降)で、その効果を深く実感できるでしょう。突然オーディションに通過するようになったり合格される方も!他のスクールに通われていた方は、内容やスピードに驚くかもしれません。未経験の方にはゼロから確かな技術を、経験者の方には間違った知識や固定観念の修正を徹底的に行います。
④オーディション対策という名の、本質的な表現力アップレッスン!
「オーディション対策」と銘打ってはいますが、その本質は俳優・声優志望の方だけでなく、あらゆるアーティストの表現力を底上げするための場として設けました。
「歌詞が棒読みになってしまう…」「セリフに気持ちを込めてしまう…」「お遊戯会のような演技から脱出したい…」「声に豊かな表情をつけたい…」「間の演技を学びたい…」「とにかく表現力をあげたい…」「ステージングを学びたい…」
そんな悩みを抱えている方にとって、このレッスンはまさに最強のスキルアップの場となるでしょう。
このオーディション対策レッスンでは何を学べるのか?
①基礎技術の徹底的な訓練と意識改革
「役っぽく演じればいい」「言われた通りに動けばいい」という根拠のない表面的で安易な発想から脱却し、プロの現場で求められる本質的な表現力を磨き、”よくある演劇のイメージ”からの意識改革を促します。
②オーディションで求められる核心的な能力の向上
オーディションの審査で重要な鍵となる以下の能力を、実践的なトレーニングを通して集中的に鍛えます。
「瞬発力、想像力、創造力、応用力、協調性、考察力、観察力、洞察力、実行力、喜怒哀楽の感情の幅、台本読解力」
これらの能力は、主にシアターゲームやエチュードを通して磨くことが可能です。近年増加しているワークショップオーディションにも対応できるよう、ゲーム形式課題への適応力も養います。実際に受講生からは「オーディションで同じワークが出題された!」「意図がわかった」「安心して取り組めた」という声や合格報告が多数寄せられています。毎回の「脳トレ・身体反射トレーニング」で、自身の感覚を常に確認し、意図した通りの表現を確実に実現できることを目指します。
③エチュードを通して得られる的確な役作り法とスタニスラフスキーシステムによる台本読解
オーディション会場で初めて台本を手にした際の初期対応、現場の台本を顔合わせまでにどのように読み込むか、歌稽古までにどこまで歌えるようにすべきか、など、プロの現場で必須となる事前準備や、現場の演出家、監督、審査員の意向(指示)を的確に捉え即座に対応できる柔軟性と主体性を学びます。
④短期間で創造する力を養う
実際の舞台や映像の現場では、合格してから本番までわずか2ヶ月ほどというスケジュールが一般的です。1シーンのお稽古は1回で、次は通し稽古、という場合もあります。市民劇やこどもミュージカルしか経験のない方は不安にもなるでしょう。
たとえば今回の『アニー』も、3月に本稽古が始まり、4月中旬には本公演がスタートしていました。このように、現場では非常にスピーディーに進行します。
そのため、オーディション対策特別レッスンでは現場に対応できる力を養うべく、限られた期間の中で台本を覚え、創造するという訓練を行います。台本エチュード(ステージング)では、実際の現場と同じように参加者それぞれがアイデアを出し合い、2次元の文字を立体的な表現へと変えていく作業に取り組んでいただいています。
俳優の仕事とは、演出家や監督の指示から意図を正確に読み取り、それに同期や理由づけをして表現すること。この本質的な力を身につけるために、さまざまなテーマのエチュードに取り組んでいただいております。
⑤音感トレーニング:ハモりレッスンの導入
音感を鍛えるための「ハモり」レッスンも積極的に行います。ハモり耳を養うことで、音感の大幅な向上、音痴の改善、ソロボーカリストの音程の安定に繋がります。ミュージカルオーディションでのハモりの評価はもちろん、CMや映画のオーディション、事務所における歌唱力のアピール、バンド活動への適応など、多岐にわたる可能性を広げます。
入会案内
現在の空き状況・入会の条件等は →→ 「こちらから」
※個人レッスンのため、会場やお時間等ご希望に添えない場合もございます。まずは、お問い合わせ下さい。
※未成年者ご本人からのお申し込みはできません。
※GmailとDocomoアドレス不可。こちらからのメールが届きません。ご注意下さい。
”アニー”や”冒険者たち”を受ける為にこのレッスンは必要なの?
実際のアニー合格発表時に、演出家が合格した子や最終まで残っていた方々に話した内容です。
「アニー」2025ではお教室の生徒さんがモリー役に合格をいただきましたが、今回も演出家から「講評としては、毎年そうなんですが、みんなのやってくれる歌とかお芝居が、ちょっとお行儀が良いのよね。孤児たちの話なのに、年々お行儀が良くて、しっかり教育を受けた学校の優等生みたいに見える子が少なくない。『アニー』にはそういうキャラクターは出てこない。グレースをやるなら、そこを狙ってほしいけれど、(孤児なら)もう少しバイタリティ、生命力、したたかさ、ずる賢さ、そういうところがもっともっと出てくると、もっともっと楽しいオーディションになると思って、みんなの耳に入れます。拡散してくださいね」
ーーー
拡散してください=お教室の先生方ココがポイントですよ!と仰っています。もう、毎年毎年こういう方が欲しいんです!合格できるのです!と仰られているのですよね。
アニーに限らず、すべてのお芝居に通じると思います。
お教室のこの特別レッスンでは、キッズ・ジュニア・大人にかかわらず、これに応えられるような基礎を応用を、徹底的にしつこくご体感いただいております!だから特別レッスンに参加されると、役の豊かな表現と”熱量異常”にもまれ、演出家やステージングさん、監督さんに「おっ!いいね!」と言われるようになるのです!
生徒さんが合格した2019年の発表時の演出家からの演技方針がこちら→「アニーっていう子には、明るかったり、人の気持ちが分かるというところはもちろんあると思うんですけど、ずる賢いとか、抜け目がないだとか、したたかだとか、物怖じしないとかっていう、そういう部分もきっとあると思うんですよね。あなたたちの中にある、そういう普段は隠してるところを思い出してくれると嬉しいです」。
2021年はこちら→「毎年そうだが、たくさんの魅力的な子どもたちがいて、本当に甲乙つけがたい。歌・踊り・芝居ができればいいのではなく、審査員それぞれ専門の立場から、いろんな角度で、『本当に魅力的か』をチェックしていく。一人ひとりに個性や言葉にしづらい魅力がある中で、さらに素敵な輝きが他の審査員にも伝わったのがこの2人だった」「例年のオーディションは時間との闘いです。良いところと弱点を、瞬時に見抜いて前後と比較します。ですが、映像だと時間に追われずに審査できて、気になった子をもう一度見られる。そのストックをもって昨日と今日の対面審査をしたが、悪くなかった。」
また、振り付け師うらん先生のオーディション内WSでも、アニーや孤児役に必要な心の葛藤を身体表現や歌に反映できるか、指示されたことに対して機敏に的確に表現できるか、という課題を出されております。うらん先生は演劇的ダンスを目指されているようです。
2019年アニー役を射止めた岡菜々子さんは、「週5のダンスレッスンを減らし、歌と演技に絞って練習した。最終審査まで行ったのも初めて。アニー役に受かったので心臓が飛び出しそう。元気よく笑えて、明るく、勇気を与えられるアニーになりたい。曲も覚えて帰ってもらえるように精いっぱい歌いたい。」抜群の歌唱力と評価されておりました。
これらの求められるスキルをベースとし、レッスン内容を毎回練り上げています。だからこそ、合格に近づくのです。
シアターゲーム(※詳細は「シアターゲーム」ページ参照)をはじめ、演技に必要な基礎技術が毎回のレッスンにしっかりと組み込まれています。台本の読解や役作りも、実際の演技理論を用いて深く掘り下げていくため、大河ドラマや映画など映像分野を目指す方にも大いに役立ちます。実際、映画主演に抜擢された生徒もいます。
将来的に役者として本気でこの世界を目指すのであれば、基礎の習得は避けて通れません。どこかのタイミングで必ず必要になります。もしキッズの段階でこれらの基礎を身につけていれば、審査員や監督、演出家が「おっ!」と気づくでしょう。
このレッスンは「体感型」。しっかり取り組み、気づきや感想、アンケート、さらには録画を使っての徹底的な復習を重ねることで、技術としてしっかり身についていきます。一緒に受講していた仲間が、突然「合格!」ということもあるでしょう。
ただし、演技経験が浅い方は、得た感覚がすぐに薄れてしまいます。だからこそ「維持」が大切です。お教室では月1回のレッスン参加を推奨しています。6回目あたりから、結果として目に見えて現れてくるはずです。実際、今回のミュージカル「アニー」モリー役合格も、1年弱で合格を射止めました。プロの俳優であっても、演技力維持のために定期的にワークショップに参加しています。少し手応えを感じても、油断せず地道に続けていきましょう。とにかく、維持すること。それが何よりも大切です。
ほぐし・発声
準備ができたら周りを気にせず、自分のペースでしっかりと体をほぐしていきましょう。皆に合わせるだけの惰性的な時間にしてしまっては、せっかくの時間が無駄になってしまいます。特に大人の方は、キッズに引っ張られて喉声にならないよう注意し、お腹から響く太い声を意識してください。
ウォーミングアップは、通常のレッスン時と同様に、短時間で体と声を最高の状態に引き上げるための大切な準備です。最近、自己流でただ体を動かしているだけの方が見受けられますが、表現には全身を使います。メソッドに基づいたストレッチで、隅々まで丁寧にほぐし、最高のパフォーマンスを発揮できる状態に整えましょう。
シアターゲームで脳トレ!
ストレッチのあとには、プロの現場でも実践されている「シアターゲーム」や「コミュニケーションゲーム」を必ず取り入れています。
これらは、最近主流のワークショップオーディションのみならず、NHK大河ドラマや、映画『#真相をお話しします』の撮影現場などでも使用されるなど、今ではレッスン必須のワークとなりました。
「課題のキモは何か」「どこを見られているのか」「審査員の狙いは何か」も丁寧に解説しながら進めていきます。現場で同じような形式のオーディションに出会ったとき、安心して自分らしさを発揮できるようになります。
この時間は、俳優や表現者に欠かせない「コミュニケーション力」「瞬発力」「考察力」「創造力」「想像力」「観察力」「応用力」「思考力」「洞察力」「協調性」など、多角的な力を養うトレーニングを行っています。さらに「五感」や「第六感のアンテナ」といった感覚も磨かれ、その後行われるステージング(台本エチュード)に必要な、脳と身体の神経をしっかりとつなぐ貴重な時間になります。近年注目されている「非認知能力」の育成にも、大きな効果が期待でると考えます。
また、それぞれのワークが次の課題へとつながるように組み立てているため、スムーズに意識や理解が深まるようになっています。
📍今回は「相手の意を読む」ワークに挑戦いただきました。お芝居はどうしても台本で未来を知ってしまうために”次のセリフの人”を見てしまったり、”見据えて先に動いたり”して、”ひとりで芝居をしている”状態になってしまうのですが、「相手の意を読む」という、私たちが日常行っている行為を今一度思い起こして、感覚の再現を体感していただきました。
相手の意を読み指示を的確に出せた人は、しっかりと皆がついてきてくれましたね。逆に相手の意を読まず自分のテンポだけで相手を動かそうとした人は、皆がついていけませんでした。これは送受信ワークにも通じると思いますが、いくら受信をしようと構えていても、受信者の意や呼吸を読まず一方的に飛ばしてしまうと、受信者も相手を読めずついていけないことに気づけたと思います。これが段取りで”私の番”となってしまう人の特徴です。動画でもはっきりとわかるので、できている人、できていない人の差をチェックし、次回のエチュードでは、相手の意を読んでから反応するよう意識してみてください。
ミュージカルナンバー練習
この時間では、覚えきれなかった方への最終音取り確認を行い、それぞれ担当役で歌っていただきました。前回の”参考音源とカラオケ音源”のお渡しでは難しかったようなので、今回はメロディ入りの音源をお渡ししました。譜割りが難しい部分があったようですが、ほぼ完璧に歌えた方もおりました。オーディション時には「さまざまなパターンで課題が出されます」ので、それらに対応できるよう訓練しておきましょう。
ミュージカルシーンスタディ
今月も既存のミュージカルから、歌のあるワンシーンを創り上げるシーンスタディに挑戦しました。
特別レッスンでのエチュードでは、シーンの背景や登場人物の本心を理解し、相手の反応を意識することで演技のリアリティを高めることを目的として行っています。自分の考察や練習の成果を披露するのではなく、「芝居は関係性の中で成立する」ということを学んでいただいています。
今回は設定を大きく変え、大人と子どもが混ざった環境で、どう絡み合うかに重点を置いてステージングを行いました。感想にもあった通り、こちらが背景設定を細かく指示すれば、それらしく演じられた…といった状態でしたね。もっと想像力を働かせましょう。
一人芝居でない限り、お芝居は一人では成立しません。今どんな状況なのか、どんな関係性の人物がいて、何を見せるシーンなのか。何を伝えるべきなのか、セリフや感情のベクトルを明確にし、シーンの目的に近づけていきましょう。皆”個”になってしまった為、キャッチボールができず、心があまり動かなかったのではないでしょうか。台本を受け取ったらまず、セリフへの裏付け、確信の持てる答えを見つけるところからはじめましょう。

お教室のエチュードは基本的に群像劇です。それぞれの人生を生きている人を演じますので、”モブ”という概念は捨ててご参加ください。お教室に限らず、”モブ=○○”という指定がない限り、セリフがない、動きの指定がない、なぜ居るかわからない出演者=モブ、ではありません。ステージ上にいる人は必要があってそこに居るのです。自分の役のシーンの目的を遂行しましょう。
また文字依存し、状況が変わっても毎回同じ言い回しになってしまった方もいました。相手の意図を読み取り、役として相手の言葉をしっかり受け止めれば、よりリアルな反応が生まれます。今回は、自分が嘘をついているにもかかわらず、文字通り正当化をしてしまい「嘘をついていないように見える」演技になってしまいました。とぼけなければ成立しない場面もあるので、自分の役の目的をしっかり意識することが必要です。他の現場でも臨機応変に対応できるよう、今後も訓練していきましょう。
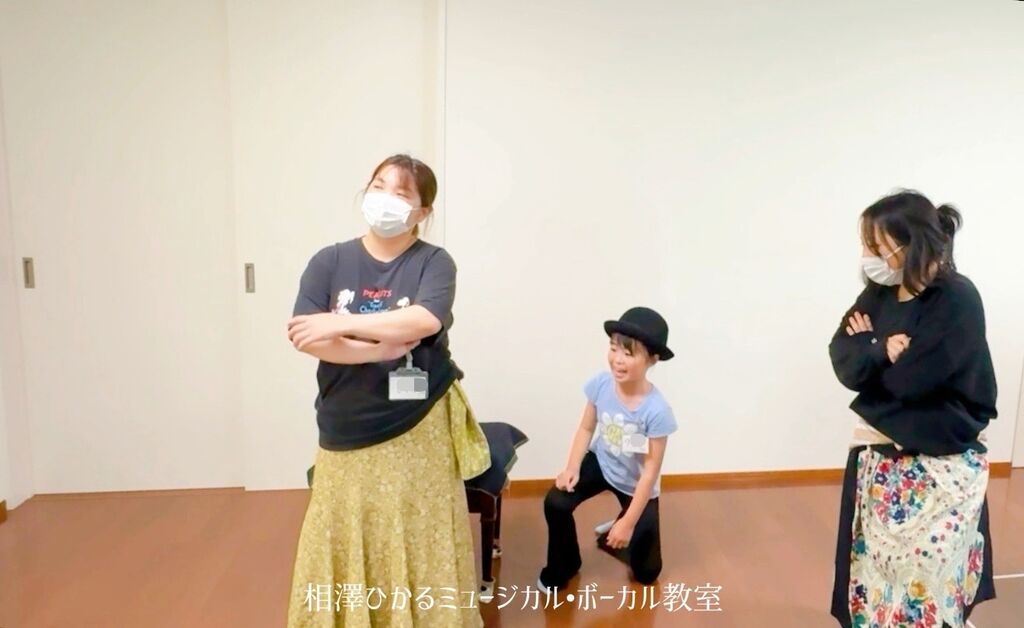
👉 歌を覚えることに精一杯で、当日は歌うことで手一杯だった方。次回は新作に挑みます。新しい台本と曲を覚えますので、人一倍時間がかかることを想定し、届いたらすぐに全体を確認し、練習を始めてください。すでに発表になった楽曲はどんどん練習してくださいね。今回使う楽曲も、昨今の子役ミュージカルオーディションに対応したものです。確実に歌いこなしましょう!
ーーーー
役者のお仕事は「役になりきる」のではなく、「役としてこの世界で生きる」ことです。(今回一番下に、劇団四季創設者浅利さんの言葉をのせています)早くセリフ(文字)依存や段取り依存から抜け出しましょう。誰の言動(きっかけ)を受けるわけでもなく、自分が安心する自宅練習でのテンポのまま毎回セリフを言ったり、同じ動きを惰性でなぞっているだけでは、ひとり空回りで上達はできませんよ。
役者はマルチタスク必須です。脳と心と体を研ぎ澄ませ、しっかり対応できるよう万全な態勢で臨んでください。マルチタスクの苦手な方は「対戦ゲーム」がおすすめです。
未入会だけど・・・参加したくなった!
オーディション対策レッスンは、月に1回、月末あたりの週末に開催しています。対象は小学1年生〜30代まで。
このレッスンでは、参加者全員にすべてのワークに取り組んでいただき、個別に丁寧なアドバイスを行ったうえで、何度も繰り返し確認(小返し)をします。そのため、定員は3名から8名までの少人数制。参加者が多い場合には、時間を分けて対応しています。
グループレッスンでよくある「アドバイスをもらって終わり」という状態では、本当の意味で身につきません。アドバイスをもらった内容を自分のものにするには、繰り返し実践することが必要です。しかし、多くのスクールや事務所のレッスンでは、時間や人数の関係でこれが難しく、表面的な知識だけが残ってしまうこともあります。
ここでは、「本当にここまでやってくれるの?」というほど現場に直結した実践型のオーディション対策を行っています。読んでいて「ちょっと参加してみたい」と思われた方もご安心ください。普段のレッスンに通っていない方でも、「単発レッスン生」としてご参加いただけます。詳細は→「単発レッスン」ページをご確認ください。
なお、このレッスンには課題があるため、エントリーには締切があります。また、内容も高度なため、事前に必要な準備レッスンを受けていない方はご参加いただけません。
「難しそうでついていけるか不安…」という声もありますが、実際のオーディション現場はもっと厳しいもの。だからこそ、今のうちにその環境に慣れておくことがとても大切なのです。

受講生の感想とアンケート
アンケート(気づき・感想)は、レッスン後に振り返りを行い、自分の中での学びや課題を整理するための大切な時間です。「できた」「できなかった」「よくわからなかった」など、今の段階での気づきを言葉にすることが上達の過程でとても重要になります。毎回、多くの気づきを丁寧に書き留めている方もいらっしゃいます。
技術的にまだ準備が整っていない方に対しては、合同レッスン中に細かな修正アドバイス(ノーツ)を加えることはほとんどしていません。というのも、アドバイスを受け取るための知識や準備が整っていない段階では、言葉だけが空回りしてしまうからです(ただのダメに聞こえる場合も)。しばらくはその方のペースを見守り、繰り返し特別レッスンを受けていただく中で、体感として理解できるようになってきたと思われるタイミングで、本格的な指導が始まります。
アンケートを書くのが面倒に感じられることもあるかもしれませんが、自分が何に気づき、何にまだ気づけていないのかを共有していただくことで、今後の課題がより明確になり、個人レッスンでの振り返りも一層深まり、スキルアップにつながります。
なお、レッスンの「ねらい」や「核心」部分の気づきについてはこちらには記載していません。中には素晴らしい洞察を得ている方もいますが、その内容は実際にレッスンを受けて体験していただくのが一番です。他にはない、現場に直結した超実践的な内容を、ぜひご自身で体感してみてください。

皆さんの気づき・感想は、数百個となる場合もあり、こちらで集約しワークごとに仕分けするため、メールテキスト(メモの写メNG)で送っていただいております。気づきが多ければ多いほどすばらしいですよ!気づけたことはできるようになります。気づけないことはできるようになりません。
◉気づき・感想・アンケートの書き方
レッスン後の、気づき・感想・アンケートは「所感と現実の差を埋める」ための大事な作業です。できるだけ早く、まだドキドキが残っているうちに以下の5つを意識して書いてみてください。
① ワークの中で、自分はどんなことを感じた?どう思った?
② 「できた!」と思った? それとも「うまくできなかったな…」と思った?
③ 他の人のパフォーマンスやダメ出しを見て、どんな気づきがあった?
④ これから自分はどうしていきたい?
⑤ 後日動画を見て、自分の感覚とどう違っていた?(もし見れない場合は、ノートに今の時点での気づきをメモしておこう!)
また、レッスンで学んだ技術的なことは、ご自身のノートにも残しておくと後で役立ちます。
もし2時間のレッスンで気づけたことがほんの数行しかなかったら、観察力がまだ弱いか、もっと試したい!という気持ち、事前準備(これを試したい)が足りないかもしれません。
また、現段階では「何ができてて」「何ができてないか」がまだピンとこない人もいると思います。5回くらい参加していく中で、少しずつ見えてくるはずなので、それまで他の人のアンケートからもイメージを広げておいてくださいね。
なお、ここは「批評」や「観劇の感想」を書く場ではありません!(作品として成立していたときは別です)大事なのは「自分はどうできたか・できなかったか」「考察を試した結果どうだったか」「他の人は何を持ち込んでどうだったか?」その“気づき”を残すことです。
振り返りは時間もかかるので、ちょっと面倒に感じるかもしれません。が、WSなどは受けただけでは変わることはできません。この見直し作業こそが力になります!「できなかったこと」「気づけなかったこと」は、個人レッスンで一緒に深めていきましょう。この地道な積み重ねが、確実にスキルアップ・視野アップにつながっていきますよ。
○2025.08 気づき感想がなかった方、自分の番だけ頑張る、他はただ見ているだけ、では上達できません。お遊戯会から脱出するには、観察力をもっとつけましょう!
→発声・送受信
・受信する側の時に相手の裏の言葉をエネルギー量と合わせて考えるようにした
・貰ったらちゃんと反応するよう意識したけどちゃんと言葉に出来てなかった
・興奮すると踵が上がってしまうので、ちゃんと言葉にして気持ちを上げれるようにしたい
・皆さんよりも深さが明らかに浅く体力不足を感じた
→シアターゲーム
・速い方が興奮して楽しい感覚があった。セリフのスピード感の興奮と近いような気がした。
・Aさんの時に速いなと思い、自分がついていけてないだけかと思ったけど相手に合わせるのも必要だと分かった
・Bさんの時、間が合って次に動く時の呼吸を感じたからやりやすかった
・お芝居もどんどんいくのではなくて、相手の呼吸や間をもっと感じながらお芝居したいと思った
・自分が親の時に、”前後の動作に無駄な動きを入れない”ことを意識した。無意味な動き、無駄な動きを入れず、次にやる動作の準備動作のみが目立つようにしたことで、伝わりやすかったように感じる。やりながら、まさに「演劇の時に無駄な動きをしない、意味のない動きをしない、無意味に見ない、顔を向けない」等を実感として理解できた
→参考動画
・声をバトミントンのように打ち返してるような軌道が見えたような気がした
(A:9月以降のの特別レッスンミュージカルでぜひ試してみてください)
・何を言ってるか聞き取れなかったけど説得力的なのを感じた。熱意?エネルギーが凄かった
・ドラマで観た人達の滑舌良く、口も大きく開けてハキハキ喋っていた。ドラマの時の雰囲気とは違っていた
・ちゃんとギャグなんだと分かるような空気の変わり方、声色も出たりして凄かった
・アンサンブルが、しゃべっていないのに小さな演技をしていて、しっかり生きていた
→音階発声・ナンバー練習
・リズムを落とし込めてないから、リズム中心、歌だけに集中して役として歌えなかった
・急な変更を直ぐに覚えられていなかったから歌詞カードに目がいってしまった
・歌のリズムを理解しきれておらず、メロディをつけて歌うとメロメロになってしまってご迷惑をかけた
・腕を振りながら歌うとスイスイ歌いやすく歌えて、リズムを体が感じるとすらすらと言葉が出るのだなと思った
→ミュージカルシーンスタディ
”自分”ができたか、できなかったか、の気づきだけでなく、他の人のいい演技や自分では思いつけなかった面白いアイデアを持ってきていることにも気づいていこう!
・警察のことをすっかり完全に忘れていた。そもそも、そこでなんで歌っている?どんな気持ちで?というのをつくれていなかった。
・ねずみがいるけどね!はは!みたいな気持ちでベットに話しかけたかった(かけたつもり)だったが、段取りになってしまったと感じた
・恋人の話をする時、ちゃんとその人の話を聞いて受け止めてから話そう、と意識した。でも意識しすぎて段取りになってしまったかもしれないと感じる
・皆さんは小返しの時はすごく素敵だったけど、やればやるほど(?)なぜかのんびりとした感じになり、一番最初が良いような気がした。慣れることで、なぜかスピード感がなくなると感じた。
(A:慣れ・ダレと言います。皆が段取りを覚えそればかりに集中すると新鮮さは失われます。いつもドキドキしていることが必要。)
・歌う前の最初の出だしを大事にしたので、最初流れに乗れたのにその後直ぐに流れが落ちて繋がらなくなった気がした
・歌に集中しすぎて、目的や超目的が全く分からなくなってしまった
・相手との関係性も全て段取りで会話をするようなやり取りしか出来ず心が動かなかった
・先生から動機や動きを教えてもらって皆がその目的の為に動く時だけそれっぽくなった気がした
・歌や台詞は必ず落とし込まなければお芝居として成立出来ないんだと思えた
・チョコのシーンだけ、関係性やステータスを意識して動いてみた。ですがその後はもうわからなくなり忘れてしまいました(関係性を意識することを)
・(振り返り後)相手を動かすにはそれなりのエネルギーが必要だからちゃんと動機も付けて相手を動かせるように次回試したい
・(振り返り後)ずっとお酒飲んだ姿にしてしまって、場所が変更した事をちゃんと理解せずおかしな動きをしてしまった
→6.誰かから心が動かされましたか?
・練習の小返しの時のAさんがハンカチを奪うところ
・冒頭のシーン、つまみ食いしているのを発見した時
→本日のMVP ! 一番すごかった人!
Aさん こっそりテーブルのお菓子を食べるところ
Bさん ゆっくり歌う箇所を気持ちを込めて歌っていた
→アンケートの意義と活用法 〜気づきが“できる”をつくる〜
アンケートでは「できた」「意識できた」とチェックされていても、実際には体現できていないケースも見受けられます。そのような場合、ご本人が「もうできるようになった」と勘違いしてしまっていることが多く、気づきメモからも体感に関する記述が消えていきます。こうした状態に陥っている方には、特別レッスンや個人レッスンで改めて取り上げ、「まだできていないことを自分で認識する」ための訓練を行っていきます。これは経験量とも深く関係していますので、特別レッスンを重ねて体感を積み上げていくことが大切です。
また、前回「よくわからなかった」と記入していた方が、今回も同じチェックをしているにもかかわらず、それに関する振り返りがない場合もあります。「何がわからなかったのか」「前回と何が違ったのか」など、たとえ不明点が残っていても、それを言語化すること自体が大きな成長の一歩です。ぜひ記載してください。
よくある例として、他の人がアドバイスを受けてできるようになったのを見て「自分もわかった気になる」パターンもあります。でも、それはまだ“自分の引き出し”にはなっていません。他の人から知識として学ぶことは大切ですが、それを自分の中に落とし込み、必要な場面で使えるようになってこそ、本当に“使える力”になります。オーディションではこの「引き出し」が命です。
また、体感だけを書いて終わるのではなく、見学を通して感じたこと、他の人の演技から学んだことも、積極的にメモに残してください。アドバイスからの変化も、自分の財産にしていく気持ちで残しましょう。
アンケートは、当日の所感を書くことが前提です。書いたら終わりではなく、自分の当日の感覚と実際の演技とのギャップを、動画を見ながら研究し、日々のレッスンで埋めていきましょう。
皆さんの感想は、すべてが「正解」というわけではありません。長く通っている方や、できるようになってきた方の中には、「これは違うな」と感じることもあるでしょう。でも、それも自分が通ってきた道。誰しもが通る段階です。他の人の所感を読むことで、自分自身の成長を感じてみてください。また、皆の感想にはヒントもたくさんあります。次回のためにしっかりメモを取りながら読んでみてください。
◉「役になりきる=演じる」と思っているうちは、自分自身が完全には消えておらず、その“自分”が心のどこかに残っているため、恥ずかしさや人の目を気にする感情が抜けきれません。その結果、表面的で“お遊戯会”のような演技になってしまいます。これでは、役としてリアルに生きることはできませんし、観ている人も気まずさや違和感を抱いてしまいます。本来伝えたいこととは真逆の結果になってしまうのです。プロの演技とは?役者の仕事とは?ぜひ、このレッスンで実際に体感してください。
2025年9月以降の特別レッスン
9月10月11月(来年2月まで)は、新しい台本でのミュージカルレッスンが始まります。台本読解から役作り、歌、表現等、現場ではどのような技術や意識が必要かを、この作品創りを通してお勉強として学んでいただきます。全役ソロありの感動する群像劇です。お楽しみに!
前回の特別レッスンレポートにキービジュアルも掲載しておりますので、イメージをぜひご覧ください。(一部変更あり)
なお、マイページ内「お知らせ」には2026年3月までの特別レッスン日程を記載しました。日程のご準備をお願いいたします。
以前のオーディション対策レッスンレポート一覧
今までのオーディション対策レッスンの記事が一覧になりました❗️
オーディションを受ける方は必見❗️このレッスンを受けた方が続々と中央で活躍中❗️一緒に受けているメンバーも刺激を受けます。セミプロ以上を目指す方や、お教室に入会希望の方も、ぜひご覧下さい。
レッスン内容の詳細が書かれていない?具体的に何をやっているの?と思われるかもしれませんが、参加された方のみが合格やスキルアップできればいいので、こちらには記載いたしません!もちろん生徒さんのブログでも「肝」は記載していないと思います!内容はぜひレッスンでお試しください (^_^)
おまけ:劇団四季浅利代表の”役者たるもの”
劇団四季オーディションを目指す方もここを読んでいると思います。浅利先生が常日頃役者さんたちに伝えていた”役者たるもの”について、団員の阿久津さんがポストしておられたので参考にアップいたします。なお、誤解があるといけないので、相澤が補足を追記します。
<補足>
相澤も「役になりきる」「気持ちを込める」と言う言葉は捨ててと言いますね。
居る=役としてこの世界に存在する・役そのもの
聞いて=役として相手の話を聞き反応する・意を読む
捨てて=自分自身を捨てる・決められた段取りで動かない
語れ=役としての考え・意見・裏の思いをセリフにのせて述べる
(演出に文句を言う!ではありません)
消える=自分自身を消す・段取りを思い出して動かない
です。四季に限らず、お芝居の根本はココ。
浅利先生は
— 阿久津陽一郎 (@YohichirohA) August 27, 2025
『「居て」「聞いて」「捨てて」「語れ」。役に成り切るのをやめろ!役の前で透明になって消えるんだ!』とよくおっしゃいました。
「居る」とは作品の状況に存在し続ける事
「聞いて」とは相手の考えを読み取る事
「捨てて」とは「やってやろうとする事」を無くす事…